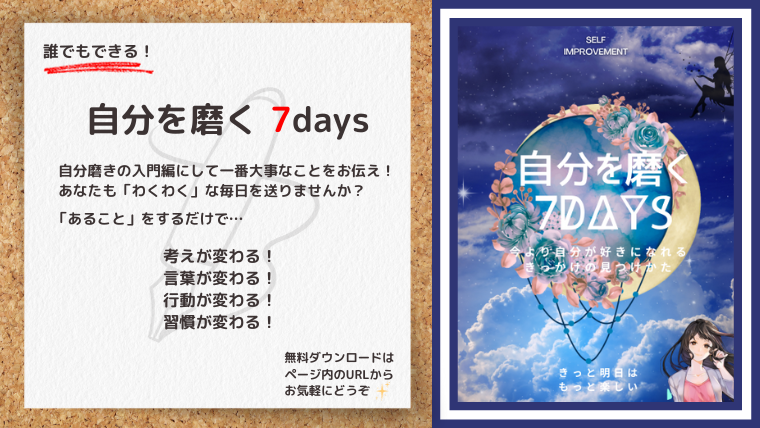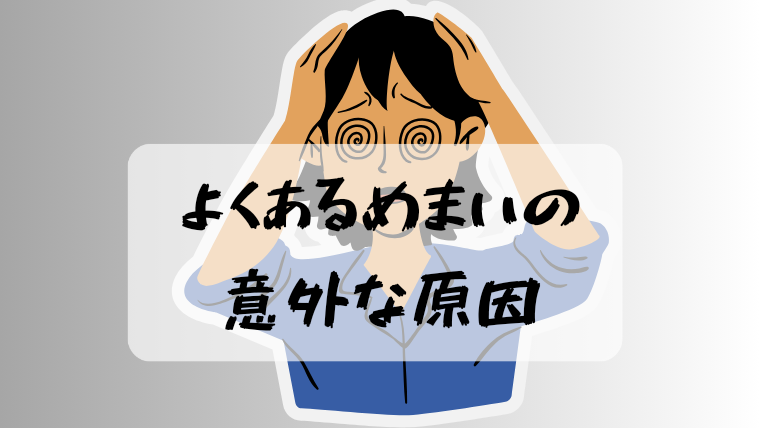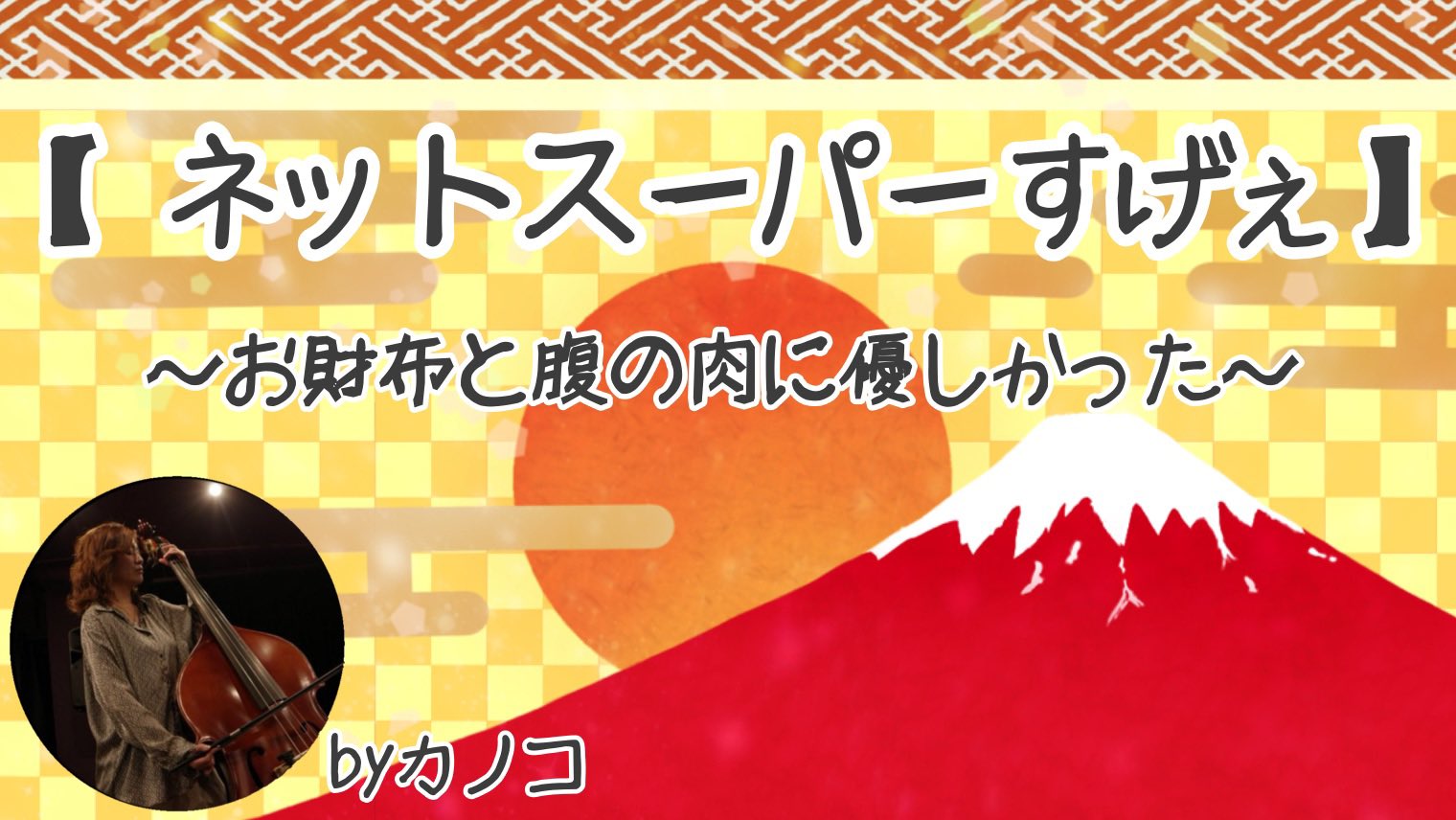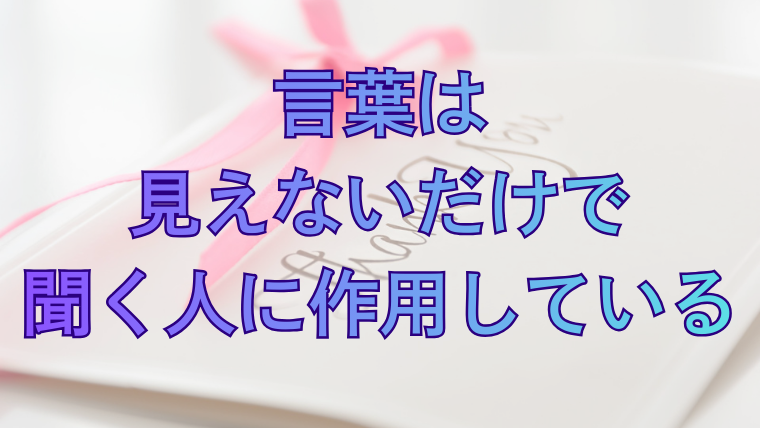起立性調節障害を“本質”から考える

── 健康オタク母の7年の探究と経験をもとに ──
はじめに
これは、起立性調節障害(OD)の本質を理解するための資料です。
起立性調節障害とは、思春期前後に多くみられる“自律神経の不調”による病気です。
朝になると「頭が痛い」「気持ち悪い」「吐き気がする」「お腹が痛い」と言って、布団から出られない。
真面目な子だったのに、どうして学校に行けないのか──親の私も、当初は戸惑うばかりでした。
朝調子が悪くても午後には落ち着く場合も多いため、怠けやサボリと誤解されやすいのです。
そして、理解されにくい病気だからこそ、長く苦しむ子どもも少なくありません。
実は、医師向けの全国的な指針(ガイドライン)にも「これさえすれば治る」という決定打となる治療法は示されていません。(ガイドラインはリンク集に載せています。)
私は、娘がこの病気と診断されるまでに約5年、そこから回復までにさらに2年かかりました。
この経験をもとに、病気の理解に役立つ情報をまとめました。
①起立性調節障害の主な症状 ②起立性調節障害のイメージ
③治療の現実 ④背景にあるもの ⑤先生や家族へのお願い
この5つをお伝えします。
ご家族や先生方に読んでいただけたら嬉しいです。
①起立性調節障害の主な症状
・ 朝なかなか起きられない
・ めまいや立ちくらみ
・ 頭痛・吐き気・腹痛を訴えることも
・ 動悸や息切れを感じる
・ 午後は少し元気になる場合も
・ 学校に行けない日が増える
・ 顔色が青白く、元気なさそうに見える

② 起立性調節障害のイメージ
私は、起立性調節障害を「朝エンジンがかかりにくい車」にたとえています。(私なりの解釈です。)
朝、アクセルを踏んでもすぐには反応しない。
しばらく待って、ようやくエンジンが温まってきたら走り出せる。
でも、次の日の朝にはまた同じようにエンジンがかかりにくくなる。
「やる気がない」のではなく、体の状態がそうなっているのです。

③ 治療の現実
起立性調節障害は、医師向けには診療ガイドライン(全国指針)が作られています。
水分・塩分の補給が勧められることもあります。しかし、その中で決定的な治療法は示されていません。薬を使う方法もありますが、それだけでの解決は難しく、長く患う場合も多いです。
そのため、生活の工夫や周囲の理解がとても大切になります。
④ 背景にあるもの
起立性調節障害の背景には、いくつかの要因が重なっていると私は考えています。
1. 成長期に特有の体の変化
体をつくるために大量の栄養(鉄やタンパク質など)が必要で、体づくりに栄養が優先され、エネルギーを作るための栄養が足りなくなりやすい。車に例えると、ガス欠。
2. 栄養と吸収の問題
現代は昔と違い、ビタミン・ミネラルなどが不足しやすく、エネルギー効率も低下しやすい。消化・吸収・代謝(エネルギ作り)がうまくいかない場合も。車に例えると、潤滑油不足、エンジン不良。
3. 心の変化とストレス
自我が芽生える時期で、人間関係のストレスも大きく、自律神経が乱れる。車だと、アクセル・ブレーキ不調でしょうか。
⑤ 先生や家族へのお願い
- 無理に会おうとしない
(体力を消耗します)
- 無理に言葉を引き出さない
(しんどさを言わせなくて大丈夫です)
- 学校に関係ない「好きなこと」の話題でつながる
(安心やエネルギーにつながります)
- その子の個性やペースを尊重する
(安心感がエネルギーになります)
私の娘の場合、授業に出られなくても「遊びや好きなことを楽しむ時間」を大切にして支えました。
その時間がエネルギーになり、回復の足がかりにもなったと今は感じています。
おわりに
起立性調節障害は、子どもの努力不足でも、親の育て方のせいでもありません。
体の状態の不具合で病気になっていると理解してもらえると、子どもは安心し、親も救われます。
そして、その理解は先生や家族にとっても、子どもとの関係をより良くする力になります。
どうか、この病気を「怠け」や「サボり」と誤解せず、子どもたちを見守っていただければ嬉しいです。
参考リンク
・診療ガイドライン(日本小児科学会)
・日本小児心身医学会:起立性調節障害
・note(体験記・発信)
・メルマガ登録はこちら

👤 著者プロフィール
KenkoVoyage 百道智子(さとち)
健康オタク母。娘が起立性調節障害と分かるまでに約5年、
そこから元気を取り戻すまでに約2年。
親として迷い、試行錯誤して得た知識と経験をまとめ発信中。
悩んでいる親やご家族、先生方の助けになればと願っています。
note版では、この記事のPDF版をダウンロードできます。
さとちのメディア
サブアカウント