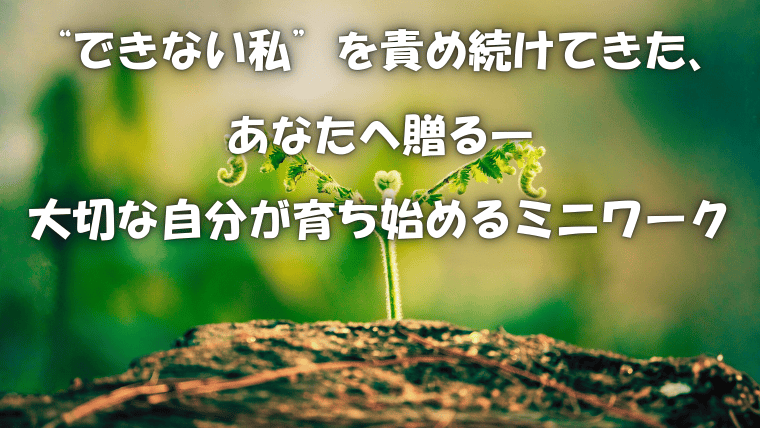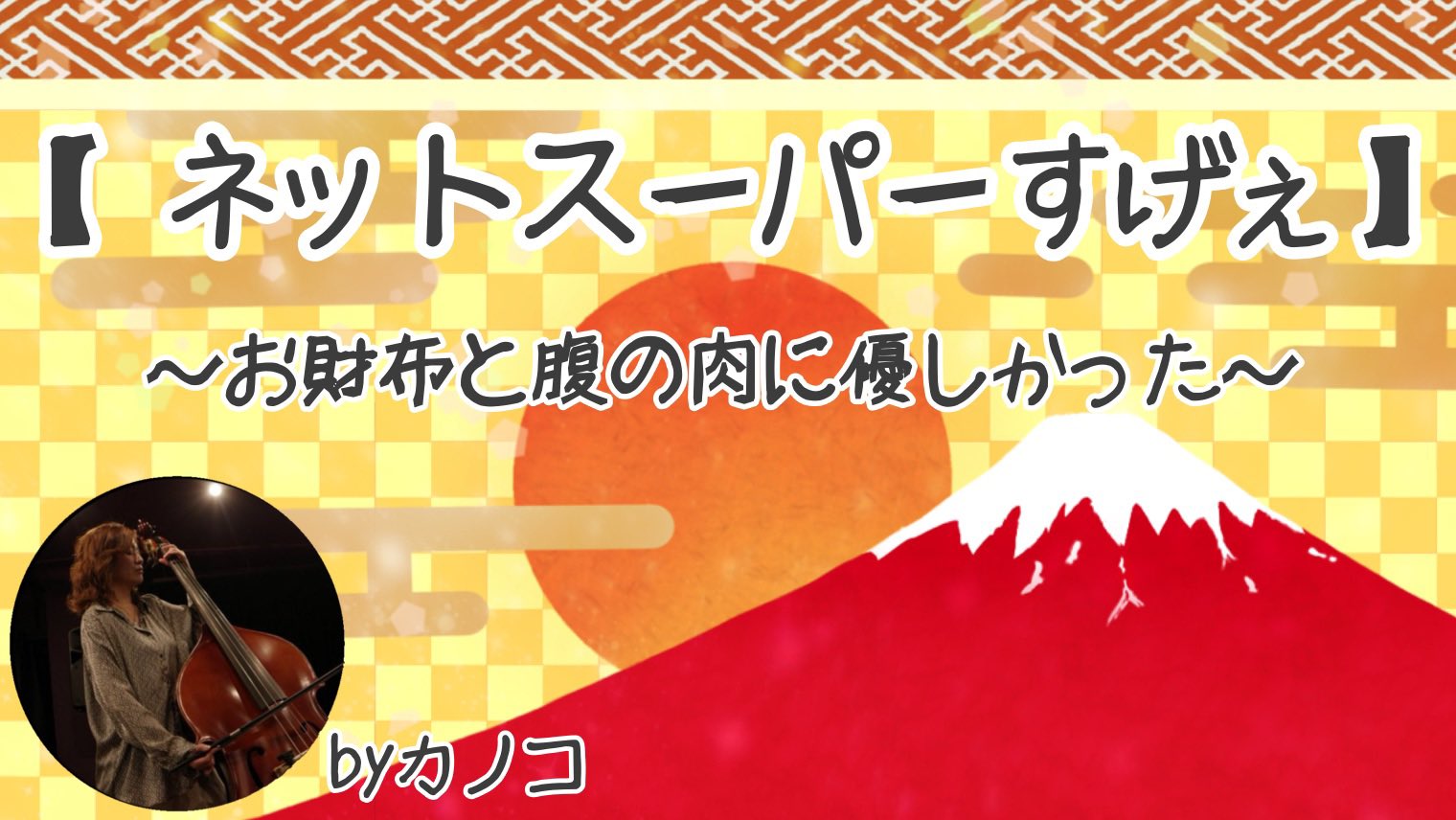起立性調節障害の本質と“親ができるケア”のヒント

はじめに
こんにちは。「KenkoVoyage さとち」と申します。
このnoteは、起立性調節障害のお子さんがいる親御さんへ向けて書きました。
私の娘も起立性調節障害でしたが、今は回復し、大学を卒業後、社会人として自立しています。
私と娘の経験から見えてきた起立性調節障害の本質と“親ができるケア”のヒントをまとめました。
押しつけでもなく、専門家目線でもありません。
ひとりの親として、「あなたと同じ立場」で書いているnoteです。
私はもともと健康オタク気質で、自分の体を整えることに関心がありました。
花粉症で薬が手放せなかった時期もありましたが、断食や食事の見直しなどで、薬に頼らず過ごせるようになった経験があります。
だから、「医療は万能じゃない」という感覚や、「家庭でできることもある」という視点は、もともと少しは持っていました。
でも、娘が体調を崩しはじめたとき——
最初は「風邪かな?」「ちょっと疲れてるのかも」そんなふうに思ったんです。
まさか病気だなんて、思いもしませんでした。
少しずつ学校を休む日が増えていく中で、私は不安でたまらなくなり、
「何が起こっているんだろう」と、パソコンで検索しまくっていました。
子どもを図書館に連れて行ったついでに、自分も本を借りて読んだり。
でも、当時はスマホも持ってなくて、情報も今ほど手に入りませんでした。
起立性調節障害という言葉も、おそらくその頃は知らなかったと思います。
そして、当時は分かりませんでしたが、症状を振り返ってみると、おそらく小3の頃からすでに、起立性調節障害だったと思うんです。
完全に登校できなくなったのは、小学3年生の3学期。
「これは不登校だ」と思い、講演会に行ったり、紹介された親子カウンセリングに通ったりしました。
幸い、そのときは2ヶ月ほどで学校に通えるようになりました。
でも、その後も体調の波や気持ちの揺れはずっと続いていて…
起立性調節障害と診断されたのは、それから約5年後でした。
「もっと早く、この視点にたどり着いていたら…」
そんなふうに思うことが、たくさんあります。
このnoteに書いてあるのは、ゼロから手探りで歩いてきた道を振り返って描いた“ラフな地図”の入口です。
それでも、今のあなたの道しるべにはなるかもしれません。
あなたの子どもも、あなた自身も、今よりちょっと楽になる何かが見つかりますように。
このnoteが、そんな「小さな灯り」になれたら嬉しいです。
第1章:「なんかおかしい」けど、誰も教えてくれない現実
「頭がいたい」「気持ち悪い」
そう言って、布団から起き上がれない朝が出てきました。
体はぐったりしているのに、熱はない。あっても微熱。
いわゆる“風邪”とはちょっと違うような、そんな違和感はあったんです。
当時の私は、どうしたらいいのか分からず、ただ戸惑うばかりでした。
…でも、安心してください。
あれから時間はかかりましたが、娘は通信制ではない高校を卒業し、大学を経て、今では社会人として一人暮らしをしています。
もちろん、ここに至るまでには山あり谷あり。
私自身も何度も悩み、手探りを繰り返しました。
でも、道はあるのです。
そのことだけ、まず最初にお伝えしておきたいと思います。
そして話を戻すと——
当時は、何が起きているのか分からないまま、日々をやりすごしていました。
「学校に行きたくない」と言うのではなくて、「行けない」という感じ。
でも、夕方になると、起き上がれるようになって、テレビを見たり、普通に笑ったりもする。
そのギャップに、戸惑いながらも、私は
「疲れてるのかな?」
「体力がないのかも」
そんなふうに思っていた気がします。
病院が嫌いな子だったので、病院に連れて行くという発想は、その時は頭にありませんでした。
パソコンで何度も検索していたのは覚えています。
でも、どんなキーワードで検索していたのかは、もう覚えていません。
子どもを図書館に連れて行ったついでに、自分も育児書や心の本を借りて読んでいたこともありました。
朝起きられなくて休む日が出てきて、最初は月曜日だけだったのが、次第に増えていきました。
やがて月曜と金曜を休み、さらに休みの日が増えていき……
ついには、ずっと休むようになってしまいました。
最初は「行けない」だったのが、次第に「学校に行きたい気持ちはあるけど、怖い」と言うようになったんです。
「これは不登校だ」と思って、不登校の講演会に行きました。
その後、講演会で学んだことを手紙にまとめて、先生に渡しながら相談したことを覚えています。
ただ、講演会より前に通常の個人面談などで先生に何かを話していたかどうかは、もう記憶があいまいです。
はっきりしているのは、先生に相談しても「これなら解決できる」という手応えはなかったということ。
同じクラスには、娘よりも前から長期欠席している子がいて、先生を頼っても解決できるとは思えなかったんです。
だから私は、「自分でなんとかしなきゃ」と思っていました。
その頃、夫は単身赴任中。
私自身もバタバタの毎日で、正直、“やりすごしてしまった”部分もありました。
講演会の話に戻りますね。
講演会のあと、講師の先生に個別で相談したら、こう言われたんです。
月曜日だけ休み → 月曜&金曜休み → だんだん休みが増えたのは、エネルギーがどんどん足らなくなったからでしょう、と。
その時にアドバイスされたのが「川の字で寝る」こと。
それまでは3段ベッドでしたが、畳の部屋に布団を並べて、川の字で寝るようにしました。
夜中に目が覚めたとき、すぐ横に手が届く。
それだけで、母親から“エネルギー補給”できるんですよ。
その言葉にすがるように、すぐ実行しました。
講演会で学んだことは、今でもパソコンに残っています。
先生にシェアするためにパソコンで手紙を書いたからです。
不登校の理解のキーワードは「不安」
娘も、「行きたいけど、怖い」と言っていた。
- 不安をかき消そうとしない。成長へつなげる。
- ゴールは“学校に戻る”ことではなく、“自我を強化する”こと。
- 人は誰でも、成長しようとする力を持っている。あとは、どれだけ信じられるか。
でも——
そこで語られるのはあくまで“不登校の理解”であって、体の不調を病気として説明してくれる人はいませんでした。
誰も、「それは起立性調節障害という病気かもしれない」とは教えてくれなかったのです。
当時は、きっと、周りの誰もまだその病気を知らなかったんだと思います。
だから私は、手探りで、時間をかけて、“ただの不登校”では片づけられない違和感と向き合ってきました。
そして今になって思うんです。
あの頃からすでに、あれは「起立性調節障害」だったかもしれない、と。
今これを読んでいるあなたが、「なんかおかしい」と感じているなら、それはきっと正しい感覚です。
そして今のあなたには、あの頃の私にはなかった“情報”があります。
このnoteが、その入り口になれたらと願っています。
第2章:今の医療だけでは足りない理由
娘が「起立性調節障害」と診断されたのは、小学3年の不登校から数年たった後のことでした。
診断がついたとき、ようやく名前がつき、手がかりが得られてホッとすると同時に、
「もっと早く知っていれば…」という悔しさもありました。
診断を受けてすぐに、起立性調節障害について書かれた本を買って読んでみました。
本には、薬や生活習慣、心のことなど、いろんなことが書いてありました。
でも、どれもピンとこなかったのです。
そこで俯瞰して考えてみました。
「ようは、自律神経を整えればいいってことね」
そう理解できました。
もちろん、本の中にも自律神経のことは書かれていました。
しかし、とくに強調されているわけではなかったんです。
その中から私は、それを要として受け止めました。
だからこそ、「自律神経の整えを、色々やってみよう」と思ったのです。
念のため、処方された薬も飲んでみました。
でも、効果を感じられなかったし、副作用も気になって、結局2ヶ月ほどでやめてしまいました。
通院もやめました。
もともと私は健康オタクで、花粉症の薬を手放せた経験もありました。
だから、薬や医療だけに頼らず、家庭でもできることがあるはずだと考えたのです。
ただ、このときはまだ「自律神経」にしか目が向いていませんでした。
体、心、生活環境……
いろんな要因が複雑に絡み合っていることに気づいたのは、その後の長い試行錯誤と学びを経てからのことです。
でも、この「薬に頼るだけでは足りない。家庭でできることを探してみよう」
という意識の転換こそが、娘の回復につながる大きなきっかけだったと今では思います。
第3章:私が心配でたまらなかったこと、そして今
私は心配でたまりませんでした。
「このまま体調が良くならなければ、将来どうなるんだろう」
「進路の選択肢が狭まってしまうかもしれない」
そして何より、頭をよぎったのは——
「もしかして、うちの子も…」という思いでした。
そう、ひきこもり状態の方が、私のごく身近にいたんです。
起立性調節障害は「ただの怠け」でも「一時的な疲れ」でもありません。
体の不調、心の揺れ、生活環境の影響……
さまざまな要因が複雑に絡み合って、子どもを苦しめています。
そして、診断や薬だけでは、なかなか解決できません。
私も解決までに時間がかかりました。
それでも、少しずつ「家庭でできる整え」に目を向けていくことで、娘はじわじわと元気を取り戻していきました。
そして今。
娘は全日制の高校を卒業し、大学に進学し、社会人として自立しました。
一人暮らしをしながら、自分の人生を歩んでいます。
あの頃の私が思い描いていた未来です。
だからこそ、今このnoteを読んでいるあなたにも伝えたいのです。
「希望はある」ということを。
第4章:最初の一歩は「理解と目的地」
起立性調節障害は、「怠けている」「やる気がない」わけではありません。
起立性調節障害は、病気です。
私は「朝エンジンがかかりにくい車」にたとえています。

午後になるとやっと動き出す。
これが起立性調節障害のイメージです。
朝、アクセルを踏んでもすぐには反応しない。
しばらく待って、ようやく温まって走り出せる。
でも次の日には、また同じようにエンジンがかかりにくくなる。
子どもの気持ちの問題ではなく、体の状態の不具合なのです。
もし車がガス欠や潤滑油不足、エンジン不良だったらどうしますか?
ただ「そのうち走るよ」と待つのではなく、整備しますよね。
起立性調節障害も、同じです。
私は、起立性調節障害の背景にはいくつもの要因が重なっていると考えています。
車の例えをまじえてお伝えしますね。
体
成長期には体をつくるために多くの栄養(=材料)が必要です。
その材料が不足すると、「ガス欠」になります。
また、ビタミンやミネラルが足りない、消化・吸収・代謝(エネルギーや血や肉をつくる働き)がうまくいかない場合もあります。
これは「潤滑油不足」や「エンジン不良」にあたります。
さらに、これは子どもだけでなく、親自身の体調も大きく関係します。
親の体が整ってこそ、子どもを支えるエネルギーが湧いてくるのです。
心
思春期は自我が芽生える時期で、人間関係のストレスも大きく、自律神経が乱れやすくなります。
車だと、アクセル・ブレーキ不調みたいな感じでしょうか。
ここで大切なのは、親の心の在り方です。
私たちは誰でも、“色のついたメガネ”をかけています。
青を見ても、黄色のメガネなら緑に見え、赤のメガネなら紫に見える。

かけているメガネ(=思い込み)によって、
同じ出来事でも、感じ方も反応も変わってくる。
同じ出来事でも、かけている色眼鏡によって見え方が変わるのです。
子どもの頃の体験や親からの言葉、学校で刷り込まれた価値観などから無意識のうちに色眼鏡ができます。
そのため、色眼鏡をかけていると気づきにくいのです。
でも、「自分も色眼鏡をかけているかもしれない」と気づくだけで、子どもを見るまなざしが変わると思います。
また、「課題の分離」も大事なポイントです。
例えば、宿題は子どもの課題、食事の準備は親の課題。
どこまでが自分の役割かを切り分けるだけで、不要なストレスを減らせます。
すると、家庭の空気もやわらいでいきます。
暮らし
家庭は子どもにとってエネルギー補給の基地です。
食習慣や生活リズムだけでなく、「ここにいると安心できる」という空気そのものが、子どもを支えます。
親が心と体を整えると、自然に家庭の暮らしも整っていく。
その積み重ねが、子どもを少しずつ回復へと導いていきます。
そしてもう一つ大切なのが、「目的地」を思い描くこと。
ゴールは「学校に戻る」だけでしょうか?
私はそうは思いません。
進路の選択肢が広がっていくこと。
自立して、自分の人生を歩んでいけること。
家族が笑顔で安心できる時間を過ごせること。
そして、親自身もラクになれること。
その未来を思い描くことが、整えの大切な出発点になるのです。
おわりに
ここまで読んでくださってありがとうございます。
このnoteに書いてあるのは、
- 「なんかおかしい」と感じたときの戸惑い
- 医療だけでは答えが出ない現実
- 背景にある体・心・暮らしの複雑な要因
- そして、目的地を思い描くことの大切さ
私が経験から描いた“ラフな地図”の入口です。
私は、起立性調節障害だった娘を回復へと導いた経験から、この地図を作りました。
専門家のような難しい知識ではなく、誰にでもできる一歩から。
手探りで歩いてきたからこそ描けた“ラフな地図”です。
ところどころ抜けもあるかもしれません。
でも、ゼロから進むよりはずっとラクに歩ける道だと思っています。
さらに詳しい内容は、別の形でまとめています。
周りの理解を広げるために作りました。
ご家族や先生方に伝えたいときに活用していただけます。
- 有料note
私の手書きの地図であるノウハウ編はリニューアル中、ストーリー編は作成中です。
完成したら、私のnoteでお知らせします。
もし「もっと具体的に知りたい」と思ったら、別のnoteものぞいてみてくださいね。
よかったら、noteをフォローしてお待ちいただけたら嬉しいです。
この小さな灯りが、あなたとお子さんの道を照らす助けになりますように。
さとちのメディア
サブアカウント